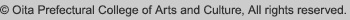公開授業2025~後期
公開授業2025~後期~
【実施期間】
2025年9月16日(火)~2026年1月16日(金)
【講義時間】
〈1限〉 9:00~10:30〈2限〉10:40~12:10
〈3限〉13:00~14:30〈4限〉14:40~16:10
〈5限〉16:20~17:50〈6限〉18:00~19:30
【受講資格】
高等学校卒業程度 ※証明書等の提出の必要はありません
【受講料】
1科目につき8,200円
各科目の授業回数はおおむね15回です。
ただし休講等発生する可能性があります。
【募集締切】
2025年9月3日(水)
お知らせ
「造形技法演習Ⅰ」「造形技法研究」「オーケストラ」について募集チラシの掲載内容に訂正があります。詳しくは、下記の「公開授業一覧」もしくは「各公開授業の詳細」をご確認ください。
受講お申込み方法
1.新規会員登録 お申し込みには、新規会員登録が必要です。高校生以下の方の受講については、 保護者情報のご登録をお願いいたします。会員登録が既にお済みの方は不要です。
※ログインの際にパスワードの入力必要です。設定したパスワードは忘れないように注意してください。下の「新規会員登録」ボタンを押すと、ログイン画面になります。 メールアドレスとパスワードを入力せずに、左下の「新規会員登録はこちら」を押してください。
新規会員登録はこちら
2.ログイン 予約サイトにログインして、該当メニューでご予約ください。お申込みから1週間経っても連絡がない場合は、芸文短大事務局公開授業担当までご連絡ください。
3.支払い お支払い方法は、銀行振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。原則としては、払い戻しや次年度への繰り越しは行っておりません。なお、振込手数料は受講者様負担となります。
4.受講 日時・場所をご確認のうえ、受講してください。皆様にとって、実り多く、楽しい時間になりますように!
注意事項
- ●諸事情によりシステム上で新規会員登録ができない場合は、事務局にお問い合わせください。
- ●受付けは先着順で、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
- ●受付け終了後、定員に満たない場合は、募集期間を延長することがあります。
- ●指定期日までに受講料のお振り込みが確認できない場合は、受講資格が取り消しとなります。
- ●お振り込み後、受講を取りやめても受講料の返金はいたしません。
- ●授業の曜日及び時間(時限)は変更になる場合があります。
- ●学期末試験は課されません。また、公開授業での単位の認定は行いません。
- ●公開授業によっては受講料の他にテキスト代など他の費用が必要になる場合があります。
- ●公開授業は授業時間内での学習を原則としており、授業時間外での質疑等には応じかねます。
- ●受講生としてふさわしくない行為等があった場合は、受講を停止する場合があります。
- ●事前カード決済はVisa、MasterCard、JCB、AmericanExpress、Diners Clubのご利用が可能です。
- ●銀行振込の方はご予約確定メールにてお振込先のご案内をいたします。予約受付システムのメニュー欄に記載されている受講料振込期限を確認の上、期限までにお振込みをお願いいたします。期日までにお振込みの確認が出来ない場合、キャンセル扱いになります。ご了承ください。










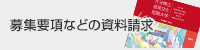
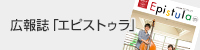
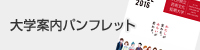
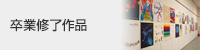
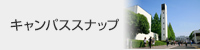
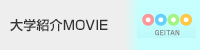

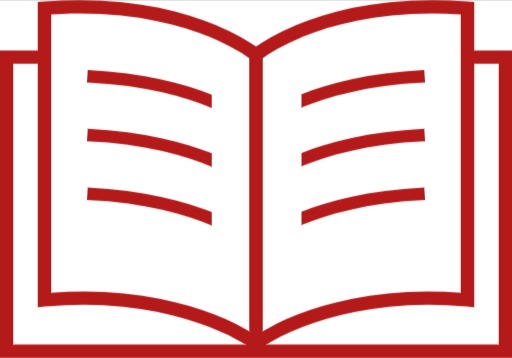 申込手順のご案内
申込手順のご案内

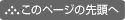
 RSS
RSS